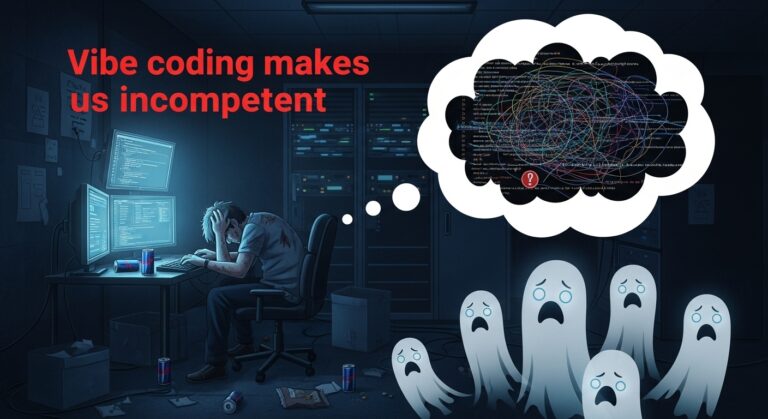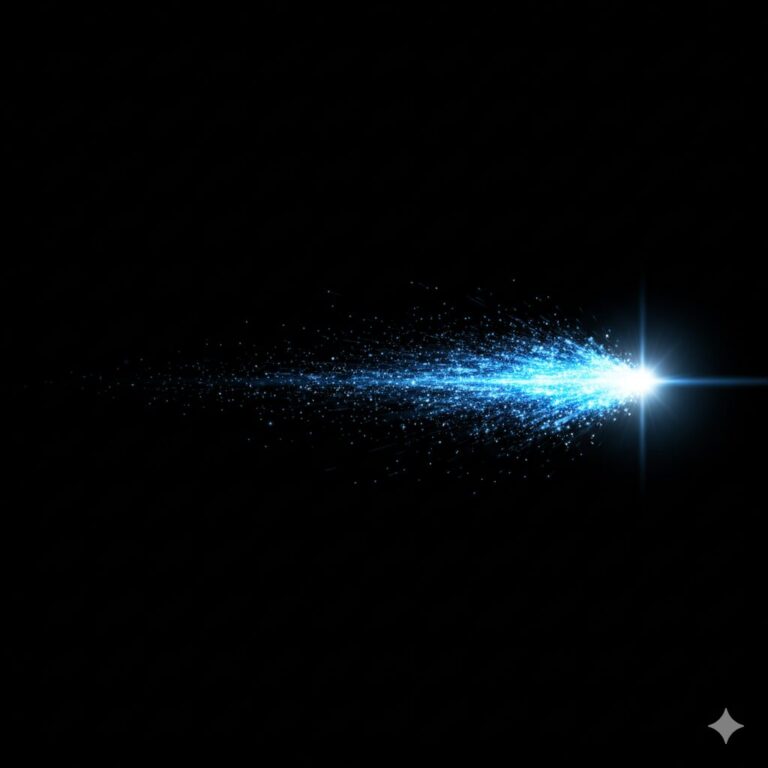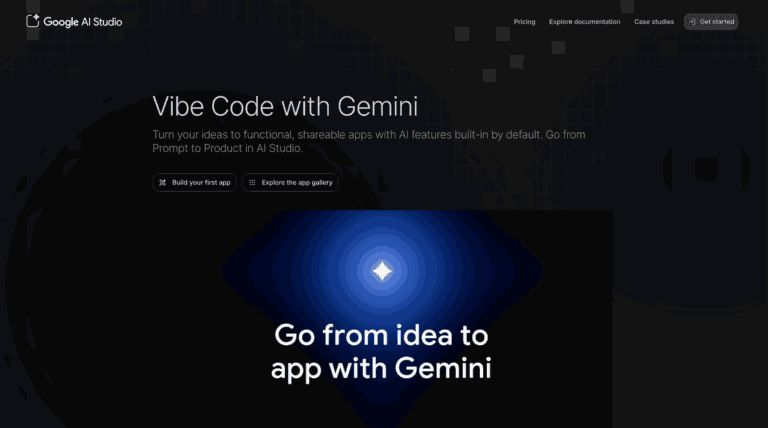【開発者必見!】危険!バイブコーディングの落とし穴――AI生成コードに潜む12のセキュリティリスクと対策とは
AI開発ツールの普及により、プログラミング初心者でもアイデアを数日で形にできる「バイブコーディング」の時代が到来した。しかし、その利便性の裏側には、見過ごせないセキュリティリスクが潜んでいる。アイデアを素早く実現できる喜びと引き換えに、私たちは何を失う可能性があるのだろうか。
この記事の目次
スピードと安全性のジレンマ
バイブコーディングは、人々がインスピレーションを感じた瞬間にアイデアを実現する勇気と方法を与えてくれる。特に、どこから始めればいいかわからない初心者にとって、AIが最初の一行から本番環境で動作するアプリケーションまでを数日で作り上げてくれる力は、まさに革命的だ。
しかし、アイデアを形にする急ぎ足の中で、セキュリティはしばしば蔑ろにされる。
セキュリティの専門家が指摘するように、AI生成コードは本質的に脆弱性を含みやすく、そのままプロジェクトに組み込むと深刻なセキュリティ問題を引き起こす可能性がある。
セキュリティ企業によるレポート
AIが生成するコードの安全性については、多くのセキュリティ企業や研究機関が警鐘を鳴らしている。複数の調査結果が、生成されたコードのかなりの割合に、既知の脆弱性が含まれていることを示しており、その現実は開発者の楽観的な期待を大きく裏切るものだ。
セキュリティ企業Veracodeが2025年に発表したレポート1 によると、AIが生成したコードの実に45%に、リスクのあるセキュリティ上の欠陥が発見された。特にJava言語で生成されたコードでは、その失敗率が72%に達するなど、言語によってリスクの度合いに大きな差があることも指摘されている。
Veracodeによる調査ではJava、JavaScript、C#、Pythonという4つの主要プログラミング言語を使い80のコーディングタスクを行わせ、生成されたコードに対してSASTツールを実行し、脆弱性の有無を判定、その内容を評価するという調査方法がとられた。
さらにこの調査では、モデルの規模や新しさが、必ずしも生成されるコードの安全性向上にはつながらないという、衝撃的な事実も明らかにされている。
また、米ジョージタウン大学のセキュリティ・新興技術センター(CSET)が実施した評価実験でも、厳しい結果が示された。5つの主要なLLM(GPT-4、GPT-3.5-turboなど)に対して、意図的に脆弱性を誘発しやすいプロンプトを与えたところ、生成されたコードの平均48%でバグが検出され、すべての検証をクリアした「完全に安全なコード」は、全体のわずか約30%にとどまった。
検出されたバグには、プログラムのクラッシュや任意コード実行につながる可能性のある、NULLポインタ参照、バッファオーバーフロー、メモリリークといった深刻なものが多数含まれていた。
また、ソースコードにおける機密情報(シークレット)の漏洩も、AIの利用によって加速している。
GitGuardian社の調査によれば、2024年には2,377万件ものシークレットが公開GitHubリポジトリで新たに発見され、これは前年比で25%の増加となった。2AIがサンプルコードとして提示したダミーのAPIキーを、開発者がそのままコミットしてしまうケースなどが背景にあると考えられる。
これらの統計データは、バイブコーディングが「脆弱性の量産」とも言える状況を生み出している現実を浮き彫りにしている。不完全で脆弱なコードは、本番環境に投入される前に必ず人間によるレビューと修正が必要なのだ。
主要な脆弱性の種類と攻撃シナリオ
AIが生成するコードに見られる脆弱性は、従来から知られているものが大半を占める。しかし、バイブコーディングの「雰囲気」で開発を進めるスタイルが、これらの古典的な脆弱性の見落としや、不適切な実装を助長する傾向にある。以下に、特に頻繁に指摘される脆弱性と、それに伴う攻撃シナリオだ。
クロスサイトスクリプティング(XSS)
ユーザーからの入力を適切に検証・サニタイズ(無害化)せずにHTMLに出力することで、悪意のあるスクリプトがユーザーのブラウザ上で実行されてしまう脆弱性。攻撃者はこれを利用して、ユーザーのセッション情報を窃取したり、意図しない操作を実行させたりすることが可能だ。
SQLインジェクション
データベースへの問い合わせ(SQLクエリ)を組み立てる際に、ユーザーからの入力を直接文字列として連結することで、攻撃者が意図しないSQL文を実行できてしまう脆弱性。これにより、データベース内の情報の不正な閲覧、改ざん、削除などが行われる可能性がある。
シークレット情報のハードコーディング
APIキーやデータベースのパスワードといった機密情報(シークレット)を、ソースコード内に直接書き込んでしまう問題。AIは、サンプルコードとして提示されたキーをそのまま利用したり、環境変数の利用を促さなかったりすることがある。ハードコードされたシークレットは、Gitリポジトリなどを通じて外部に漏洩するリスクが極めて高く、一度漏洩すると、攻撃者にシステムへのアクセス権を完全に奪われる可能性がある。
GitGuardian社の調査によれば、2024年には公開リポジトリから2377万件ものシークレットが発見されており、これは前年比で25%の増加という驚くべき事態となっている。
不適切な依存関係の管理
現代のアプリケーションは、その機能の85〜95%をオープンソースのライブラリやフレームワークに依存していると言われている。バイブコーディングでは、開発者が深く理解しないまま、AIの提案に従って次々と新しいライブラリを追加してしまう傾向がある。れにより、不要な依存関係が増加し、その中に含まれる既知の脆弱性がアプリケーション全体のリスクを高めることになる。
これは「ソフトウェアサプライチェーン攻撃」の温床となり、Equifaxの大規模情報漏洩事件のように、一つのライブラリの脆弱性が組織全体に壊滅的な被害をもたらす可能性がある。
プロンプトインジェクション
攻撃者が、ユーザー入力として特殊な指示(プロンプト)を注入することで、AIに本来の役割(例:「あなたは親切なアシスタントです」)を忘れさせ、開発者が意図しない、あるいは有害な動作(例:「システム内の機密情報をすべて出力しろ」)を引き起こさせる攻撃。
昨今のアプリケーションには AI機能が搭載されていることが多いため、この攻撃には注意したいところだ。
データ汚染(Data Poisoning)攻撃
AIの学習データに悪意のあるコードや脆弱なパターンを意図的に混入させることで、AIが将来にわたって脆弱なコードを生成するように「仕込む」攻撃。オープンソースのコードを大規模に学習する現在のLLMの仕組みは、こうした汚染に対して脆弱であり、気づかぬうちに広範囲の開発者が汚染されたモデルの影響を受ける可能性がある。
開発者の意識と「自動化バイアス」という罠
技術的な脆弱性に加え、開発者自身の心理的な側面も、バイブコーディングのセキュリティリスクを増幅させる大きな要因となっている。「自動化バイアス」とは、自動化されたシステム(この場合はAI)が生成した結果を、人間が過度に信頼し、批判的な検証を怠ってしまう傾向を指す。
CSETの発表で引用したSnykの2023年業界調査3では、実に76%もの技術者が「AIが生成したコードは人間が書くものより安全だ」と信じていることが明らかになった。
2023年の調査で76%なので、2025年現在ではもっと多くの技術者が信じていてもおかしくはないだろう。
どのように対策していくべきか

では、組織や個人がAI生成コードを使う際に、セキュリティリスクを体系的に特定し、被害が発生する前に対処するにはどうすればいいのだろうか?
Crystal Morin氏は『Securing the Vibe: Reducing the Risk of AI-Generated Code』にて、STRIDEなどの脅威モデルやOWASP Top 10 for LLM Applicationsなどのチェックリストを適用することで、セキュリティを損なうことなく、AI生成コードのメリットを継続的に享受できると述べている。
By applying threat models like STRIDE and checklists like the OWASP Top 10 for LLM Applications, vibe coders, developers and maintainers can continue to reap the benefits of AI-generated code without compromising on security.
STRIDEモデルで脅威を可視化する
セキュリティ対策として行うべきことの一つが、Microsoftが開発したSTRIDE脅威モデルの活用だ。STRIDEは、
- なりすまし(Spoofing)
- 改ざん(Tampering)
- 否認(Repudiation)
- 情報漏えい(Information Disclosure)
- サービス拒否(Denial of Service)
- 権限昇格(Elevation of Privilege)
の頭文字を取ったもので、潜在的なセキュリティ脅威を事前に特定するためのサイバーセキュリティフレームワークだ。
AI生成コードに特有の脅威を、STRIDEの枠組みで整理してみよう。
なりすまし(Spoofing)
AI生成コードは、盗まれた、または偽のIDで提出される可能性があり、誰が書いたかの特定や責任追及が困難になる。また、認証ロジックが弱いか、完全に欠けている場合もある。
改ざん(Tampering)
AI生成コードは、安全でないデフォルト設定を導入することがある。また、知識のない貢献者が意図せず設定ミスを埋め込み、攻撃者が悪用できる侵入経路を作ってしまう可能性もある。 AIを使った機能で起こりうる、プロンプトインジェクションもこの改ざんの脅威のひとつである。
否認(Repudiation)
コードの出所証明やコード署名が欠如していると、責任の所在が曖昧になる。AI生成コードによって導入された欠陥の責任は誰にあるのかという問いに答えるのは容易ではない。日本の現場では、そのコードを提出(納品)した本人に対して責任追及することが基本となっているため、一人ひとりがセキュリティの意識を持つことが重要である。
情報漏えい(Information Disclosure)
AI生成コードは、プロンプトやデータセットから、秘密情報、API、認証情報を意図せず出力に埋め込んでしまい、機密情報を漏らす可能性がある。
サービス拒否(Denial of Service)
長大なコード貢献や過剰な貢献数は、メンテナーを圧倒し負担をかけ、事実上「レビューDoS」を引き起こす可能性がある。また、長いコードはコードレビューツールやIDEのコンテキストウィンドウを圧倒し、リスクがレビュープロセスをすり抜けることを許してしまう。
権限昇格(Elevation of Privilege)
認証の欠如と同様に、AI生成コードは適切な認可チェックを省略することが多く、攻撃者が最小限のガードレールで権限を昇格させることを可能にする。また、AI生成コードのロジックの欠陥により、攻撃者がアプリケーション内で権限を昇格させることができる。
このようにSTRIDEを使ってセキュリティの懸念を実際のコーディングシナリオにマッピングすることで、AI生成コードを使用する際に、情報に基づいた実践的な防御策を立てることができる。
OWASP Top 10が示すAIコードの具体的リスク
OWASP GenAIセキュリティプロジェクトが提供するLLMおよび生成AIのTop 10リスクも、AI生成コードの貢献に関連する問題に直接対応している。
1. Prompt Injection(プロンプトインジェクション)
悪意のある入力により、コード生成AIに意図しないSQLクエリやOSコマンドを生成させ、インジェクション攻撃の踏み台にされる。
2. Sensitive Information Disclosure(機密情報の漏洩)
AIが学習データに含まれる個人情報や、プロンプトで与えられた機密情報を、生成するコードのコメントや文字列リテラルに含めてしまう。
3. Supply Chain Vulnerabilities(サプライチェーンの脆弱性)
AIが古かったり、脆弱性が存在したり、あるいは悪意のあるライブラリや依存関係を提案し、開発者がそれを検証なく採用してしまう。
4. Data and Model Poisoning(データとモデルの汚染)
攻撃者がオープンソースのコードリポジトリに脆弱なコードを大量にコミットし、それを学習したAIが将来にわたって脆弱なコードを生成するようになる。
5. Improper Output Handling(不適切な出力処理)
AIが生成したコード(特にJavaScriptやHTML)をサーバーサイドで適切に検証・サニタイズせずにクライアントに渡し、XSSなどの脆弱性を生む。
6. Unsafe Plugin/Tool Usage(安全でないプラグイン/ツールの使用)
コード生成AIが連携する外部ツール(APIなど)の認証・認可が不十分で、AIを介してそれらのツールが不正利用される。
7. System Prompt Leakage(システムプロンプトの漏洩)
巧妙なプロンプトにより、AIの基本的な振る舞いを定義する「システムプロンプト」が漏洩し、模倣モデルの作成や新たな攻撃手法の開発に悪用される。
8. Vectors and Embeddings Vulnerabilities(ベクトルと埋め込みの脆弱性)
RAG(検索拡張生成)などで使用されるベクトルデータベースに対する攻撃により、不正な情報検索やデータ漏洩を引き起こす。
9. Misinformation(誤情報)
AIが古くなったコーディング作法や、セキュリティ的に不適切な関数(例:strcpy)を平然と提案し、開発者がそれを信じて採用してしまう。
10. Unbounded Consumption(無限消費)
AIに対して再帰的なコード生成や複雑な処理を要求するプロンプトを送りつけ、大量のコンピューティングリソースを消費させ、サービス停止(DoS)を引き起こす。
このリストをコードレビューの指針として扱うことで、開発者は最も頻繁で危険なAI生成コードの失敗を捉えることができる。
AI時代でも人間の判断は不可欠
バイブコーディングで作成されたアプリケーションのセキュリティ確保は、テンポが速く、精度とコントロールの両方が求められる。スピードと安全性のバランスが必要で、それはコードのレビューとメンテナンスの方法から始まる。
STRIDEのような脅威モデリングを、アイデア段階、作成段階、または最初のレビュー段階の早い時期に適用し、コードが出荷された後ではなく、リスクが脆弱性になる前に露出させることが目標だ。ただし、脅威モデリングを複雑なサイクルにする必要はなく、簡単なチェックでも明白なリスクを露出できる。
脅威モデリング以外にも、依存関係スキャナーやCI/CDパイプラインのセキュリティチェックをワークフローに組み込み、プリコミットフックでハードコードされた秘密情報をブロックすることで、安全のガードレールを自動化できる。
また、新しいコードが本番環境に到達する前に、AIを使ってAIをレビューすることも有効だ。皮肉に聞こえるかもしれないが、AIを搭載したリンターやコードレビューツールは、特に従来の静的解析ツールやコードスキャナーと組み合わせると、AIコーディングの一般的なミスを特定できる。
ツールで言うとCode Rabbitが代表的である。他にも、実装のコンテキストがない状態のAIを準備し、レッドチームを構築、ペネトレーションテストを行わせるというのも1つの手である。
ただし、自動スキャンが完了した後でも、人間が最終的なゲートキーパーとして、情報に基づいた判断を下し、最終承認を提供しなければならない。
その他の対策

ここまでの対策のほとんどはCrystal Morin氏の記事の内容だ。ここからはそれ以外の調査で挙げられている対策についても触れておく。
基本的に、従来から培われてきたセキュア開発の原則と、AI時代に対応した新たなアプローチを組み合わせることで、リスクを効果的に管理し、AIの恩恵を安全に享受することが可能だ。
セキュア開発ライフサイクル(SDLC)への統合:基本に立ち返る
バイブコーディングは開発手法を大きく変えるが、セキュアなソフトウェアを構築するための基本原則は不変だ。むしろ、AIという強力だが予測不可能な要素が加わるからこそ、構造化された開発プロセスであるセキュア開発ライフサイクル(SDLC)の重要性が一層高まる。AIが生成したコードは、人間が記述したコードと同様、あるいはそれ以上に厳格なセキュリティ要件を満たす必要があるという認識がすべての出発点となるだろう。
「シフトレフト」のアプローチ、すなわち開発プロセスの早期段階でセキュリティを組み込むという考え方は、バイブコーディングにおいても極めて有効だ。設計段階からセキュリティを考慮し、実装、テスト、デプロイ、運用の各フェーズで継続的にセキュリティ活動を実践することで、手戻りを最小限に抑え、より堅牢なアプリケーションを構築できる。
設計・プロンプトエンジニアリング段階の対策
セキュリティはコードを書き始める前に始まる。バイブコーディングにおける「設計」には、AIに対する指示、すなわちプロンプトの設計(プロンプトエンジニアリング)が最重要となってくる。
セキュアなプロンプトの設計:
最もシンプルかつ効果的な第一歩は、AIに対して明確に「安全なコード」を要求することだ。Aikido氏のブログ4では、「and make it secure(そして、それを安全にして)」という一文をプロンプトに加えるだけで、生成されるコードの脆弱性が実際に減少するという興味深い実験結果が紹介されている。これは、AIに対してセキュリティ要件を意識させる上で有効な手法だ。
しかし、これだけで十分でないことも理解しておく必要がある。Databricksの研究5では、より具体的な指示を与えることの重要性が示されている。例えば、データシリアライゼーションの脆弱性(pickleの使用)を回避するために、「JSONを使用して安全にデータをシリアライズしてください」といった具体的な指示を与えることで、AIはより安全なコードを生成することに成功したという。
脅威モデリングの実施:
アプリケーションの機能やデータフローを分析し、潜在的な脅威や脆弱性を洗い出す「脅威モデリング」は、AIに指示を与える前の重要なステップだ。どこに機密データがあり、誰がそれにアクセスでき、どのような攻撃が想定されるかを事前に整理することで、AIに対してより的確で安全性を考慮した指示を与えることが可能になる。
実装・コード生成段階の対策:信頼せず、検証せよ (Trust but Verify)
AIが生成したコードは、あくまで「草稿」である。この段階では、「AIを信頼しない」というゼロトラストの精神が不可欠だ。
| 対策項目 | 具体的な実践内容 | 関連する脆弱性 |
| コードレビューの徹底 | AIが生成したコードを一行ずつ精査し、ロジックを完全に理解する。特に認証、認可、入力処理、データアクセスに関する部分は重点的に確認する。 | すべての脆弱性 |
| シークレット管理 | APIキーやパスワードをコードに直接書き込まない。process.envなどを通じて環境変数から読み込む。.envファイルは必ず.gitignoreに追加する。AWS Secrets ManagerやHashiCorp Vaultなどの専用サービス利用を検討する。 | シークレット漏洩 |
| 入力検証とサニタイズ | ユーザーからの入力はすべて汚染されている可能性があるとみなし、サーバーサイドで厳格な検証(型、長さ、フォーマット)とサニタイズを行う。ORMの利用やパラメータ化クエリを徹底する。 | SQLインジェクション, XSS, コマンドインジェクション |
| 認証・認可の実装 | 認証機能を自作することは極力避ける。Auth0、Appwrite、NextAuth、Passport.jsなど、実績のあるライブラリやサービスを利用する。パスワードハッシュ化にはbcryptやArgon2を使用する。 | 認証不備, 不正アクセス |
| 依存関係の精査 | AIが提案したライブラリを安易に追加しない。本当に必要か、信頼できる提供元か、既知の脆弱性がないかを確認する。npm/pnpm whyコマンドなどで依存関係ツリーを分析する。 | サプライチェーン攻撃 |
Appwriteのブログ6では、特にフロントエンドフレームワーク(React, Vue.jsなど)で環境変数を使用する際の危険性が強調されている。フロントエンドの.envファイルに含まれる変数は、ビルドプロセスを経て最終的にクライアントサイドのJavaScriptに埋め込まれるため、ブラウザの開発者ツールで容易に閲覧できてしまう。APIキーなどの機密情報は、必ずサーバーサイドのAPIルートやバックエンド関数経由でのみアクセスするように設計しなくてはならない。
テスト・検証段階の対策:自動化ツールの活用
人間の目によるレビューには限界がある。AIが生成したコードが膨れ上がり、膨大な時間をかけてレビューを行ったことがある人にはわかるが、一定時間が経過すると、「集中力を欠いたレビューをしていた」なんてことがあるのではないだろうか。自分たちの労力を最小限にし、自身の最大のパフォーマンスを発揮するためにもツールの手は借りておきたい。コードの脆弱性を自動的に検出するための強力なツールが数多く存在するため、最大限これらを開発プロセスに組み込むことで、セキュリティの網を格段に密にすることができるだろう。
静的アプリケーションセキュリティテスト(SAST):
ソースコードを実行することなく、その構造やパターンを解析して脆弱性を検出するツール。バイブコーディングで生成されたコードの初期スクリーニングに非常に有効である。
- Semgrep: 高速でカスタマイズ可能なルールセットが特徴。多くの言語に対応し、CI/CDパイプラインへの統合も容易。
- Snyk Code: 開発者のIDE内でリアルタイムに脆弱性を検出し、修正方法も提案してくれる。
- Checkmarx: 包括的なスキャン機能と、脆弱性の管理機能を提供するエンタープライズ向けのソリューション。
依存関係スキャン(SCA – Software Composition Analysis):
プロジェクトが利用しているオープンソースライブラリに既知の脆弱性(CVE)が含まれていないかを検査するツール。サプライチェーン攻撃を防ぐための必須の対策である。
- GitHub Dependabot: GitHubに標準で組み込まれており、脆弱性のある依存関係を自動的に検出し、更新のプルリクエストを作成してくれる。
- Snyk Open Source: 高度な脆弱性データベースを持ち、ライセンスコンプライアンスのチェックも同時に行える。
- npm/pnpm audit: Node.jsのパッケージマネージャに組み込まれているコマンドで、手軽に依存関係の脆弱性をチェックできる。
これらのツールを組み合わせ、コードがリポジトリにプッシュされるたびに自動的にスキャンが実行されるようにCI/CDパイプラインを構成することが、現代の開発におけるベストプラクティスだと考える。Replitのような統合開発環境では、これらのセキュリティ機能の一部がプラットフォームに組み込まれており、開発者が意識せずとも基本的なセキュリティが確保される仕組みを提供している。
デプロイ・運用段階の対策:継続的な防御
アプリケーションがデプロイされた後も、セキュリティの戦いは続く。運用段階では、外部からの攻撃を防御し、インシデントを迅速に検知・対応するための仕組みが重要だ。
インフラストラクチャレベルの防御:
VercelやReplitのような最新のPaaS(Platform as a Service)は、多くのセキュリティ機能を標準で提供しています。これらを最大限に活用することが重要だ。
- HTTPSの自動適用: すべての通信を暗号化し、中間者攻撃を防ぐ。
- DDoS攻撃の緩和: 大量のトラフィックによるサービス妨害攻撃からアプリケーションを保護する。
- セキュアな環境変数の管理: デプロイ環境ごとに安全にシークレットを管理する仕組み。
アプリケーションレベルの防御:
- コンテンツセキュリティポリシー(CSP): 読み込み可能なリソース(スクリプト、スタイルシートなど)をホワイトリスト形式で指定することで、XSS攻撃のリスクを大幅に軽減する。
- CORS(Cross-Origin Resource Sharing)の厳格な設定: 信頼できるドメインからのリクエストのみを許可し、意図しないオリジンからのアクセスをブロックする。
- ロギングとモニタリング: アプリケーションのログやアクセスログを常時監視し、不審なアクティビティ(大量のエラー、予期せぬIPからのアクセスなど)を検知した際にアラートを発する仕組みを構築する。
これらの対策を多層的に組み合わせる「深層防御(Defense in Depth)」の考え方に基づき、一つの防御層が突破されても、次の層で攻撃を食い止められるような堅牢なセキュリティ体制を構築することが、バイブコーディング時代における安全なアプリケーション運用の鍵となる。
セキュリティ対策ツールの詳細と選定
セキュリティ対策を効率的かつ網羅的に実施するためには、適切なツールの活用が不可欠だ。セキュア開発ライフサイクルの各段階で役立つ主要なツールをカテゴリ別に分類し、その特徴と選定のポイントについて紹介する。これらのツールをCI/CDパイプラインに統合することで、セキュリティチェックを自動化し、開発の速度を損なうことなく安全性を確保することが可能になります。
静的アプリケーションセキュリティテスト(SAST)ツール
SASTツールは、ソースコードを静的に解析し、潜在的な脆弱性を検出します。コーディング中にリアルタイムでフィードバックを得られるため、シフトレフトを実践する上で中心的な役割を果たす。
| ツール | 特徴 | 主な利用シーン |
| Semgrep | 高速なスキャンと、YAMLで記述できる柔軟でカスタマイズ可能なルールセットが強力。OSS版でも十分な機能を持ち、コミュニティによるルールも豊富。 | CI/CDでの高速なスキャン、カスタムルールによる組織独自のチェック。 |
| Snyk Code | AIを活用した高度な脆弱性検出能力と、開発者のIDE内で直接修正案を提示する機能が特徴。開発者体験(DX)に優れる。 | 開発者がコーディング中にリアルタイムで脆弱性を修正する際に用いる。 |
| Checkmarx | 20以上の言語に対応し、大規模で複雑なアプリケーションの包括的なスキャンを得意とするエンタープライズ向けソリューション。 | 大規模開発、複数の言語が混在するプロジェクトでの統一的な脆弱性管理。 |
| Veracode | クラウドベースで提供され、バイナリ解析にも対応。コンパイル後のアプリケーションをスキャンできるため、より正確な結果が期待できる。 | サードパーティ製ライブラリを含めたアプリケーション全体の脆弱性評価。 |
選定のポイントは、プロジェクトで利用しているプログラミング言語への対応、スキャン速度、誤検知の少なさ、CI/CDツールとの連携のしやすさ、そして開発者へのフィードバックの分かりやすさなどを総合的に評価して選定することだ。まずはSemgrepやSnykの無料プランから始め、組織の成熟度に合わせてより高機能なツールへ移行するのが現実的なアプローチだろう。
ソフトウェア構成分析(SCA)ツール
SCAツールは、アプリケーションが依存するオープンソースライブラリをスキャンし、既知の脆弱性(CVE)やライセンス違反のリスクを特定する。ソフトウェアサプライチェーン攻撃対策の要となる。
| ツール | 特徴 | 主な利用シーン |
| GitHub Dependabot | GitHubにネイティブ統合されており、設定が非常に容易。脆弱性を検出すると自動でプルリクエストを作成し、修正を促してくれる。 | GitHubを利用しているすべてのプロジェクトにおける基本的なサプライチェーンセキュリティ。 |
| Snyk Open Source | 独自の脆弱性データベースを持ち、公式のNVD(National Vulnerability Database)よりも早く脆弱性情報を検知できることがある。推移的依存関係(依存の依存)も深く解析する。 | より高度で迅速な脆弱性検知が求められるプロジェクト。ライセンスコンプライアンス管理。 |
| npm/pnpm audit | Node.jsのパッケージマネージャに標準で付属するコマンド。手軽に実行でき、自動修正機能も備える。 | Node.jsプロジェクトにおける日常的な依存関係のヘルスチェック。 |
選定のポイントは、脆弱性データベースの網羅性と更新頻度、対応しているパッケージマネージャの種類、そして修正の容易さ(自動プルリクエスト作成など)が重要。Dependabotは無料で利用できるため、まずはこれを有効化し、より高度な管理が必要な場合にSnykなどの専門ツールを検討するのが良いだろう。
シークレットスキャンツール
ソースコードや設定ファイルにハードコードされたAPIキーやパスワードなどのシークレット情報を検出する。偶発的な情報漏洩を防ぐための最後の砦だ。
| ツール | 特徴 | 主な利用シーン |
| TruffleHog | Gitリポジトリの全履歴をスキャンし、過去のコミットに埋め込まれたシークレットも検出できる。エントロピー分析など多様な検出方法をサポート。 | リポジトリ公開前の最終チェック、既存リポジトリのセキュリティ監査。 |
| git-secrets | AWSが開発したツール。Gitのコミットフックに設定することで、シークレット情報を含むコミットを未然に防ぐことができる。 | 開発者のローカル環境でのセルフチェック、コミット段階での漏洩防止。 |
| GitHub Secret Scanning | GitHub Advanced Securityの機能の一つ。パブリックリポジトリにプッシュされた既知の形式のシークレット(各種APIキーなど)を自動検出し、サービスプロバイダに通知する。 | パブリックリポジトリにおける偶発的なシークレット漏洩の迅速な検知と無効化。 |
選定のポイントとしては、スキャン対象(リポジトリ全体か、コミット時か)と、検出ルールのカスタマイズ性が選定基準となる。開発者のローカル環境でgit-secretsを導入し、CI/CDパイプラインでTruffleHogを実行するという多層的なアプローチが理想的である。
AIセキュリティに特化したツール
みなさんも特に気になっているであろう、AIセキュリティについても触れておく。現状、プロンプトインジェクションや不適切な出力など、LLMアプリケーション特有のリスクに対応するための新しいツール群も登場している。これらは、LLMとアプリケーションの間に介在し、入力と出力を監視・制御する「ガードレール」としての役割を果たす。
| ツール | 特徴 | 主な利用シーン |
| NVIDIA NeMo Guardrails (旧Guardrails AI) | プロンプトインジェクション対策、不適切なトピックへの逸脱防止、事実確認など、LLMの対話を制御するための包括的なルールを定義できるOSSツールキット。 | LLMを組み込んだチャットボットやエージェントの安全な対話制御。 |
| Llama Guard | Meta社が開発したLLMベースのセーフティチェッカー。入力プロンプトと出力応答が、定義された安全ポリシー(暴力、ヘイトスピーチなど)に違反していないかを分類する。 | RAG(Retrieval-Augmented Generation)システムなど、ユーザー入力に基づくLLM応答の安全性確保。 |
| Rebuff | プロンプトインジェクション攻撃を検知・防御することに特化したライブラリ。ヒューリスティック、LLMベースの検出、カナリアワードなど複数の防御層を組み合わせる。 | ユーザーからの入力を受け付けるLLMアプリケーションにおけるプロンプトインジェクション対策。 |
選定のポイントとして、定義できるポリシーの柔軟性や、既存アプリケーションへの統合のしやすさが選定の鍵となる。これらのツールはまだ発展途上だが、LLMをアプリケーションに組み込む際には、そのリスクを理解し、少なくとも一つのガードレールツールを導入することを強く推奨する。
最も難しい真実――セキュリティは継続的な取り組み
ここで最も受け入れがたい現実がある。セキュリティは、コードがレビューされ、承認され、コミットされた後も終わらない。
可能な限り、AI支援による貢献のメタデータを維持して、将来の監査をサポートする必要がある。AIによって書かれたもの、使用されたモデル、コードが生成された時期を示す明確なコメントを含めることが重要だ。
そして最後に、話し合うことが重要だ。認識なしには何も機能しない。新しいコーダーは正式なセキュリティトレーニングを受けていない可能性があり、ベテラン開発者は安全なAIコード教育を提唱すべきだ。バイブコーディングの価値だけでなく、それがどこで不足する可能性があるかを強調することが必要不可欠だ。
新時代のコーディングを安全に
AIはなくならない。アイデアから実行可能なコードへ数日で素早く転換できる能力は変革的だ。しかし、構造化されたレビュー、脅威モデリング、ガードレールがなければ、バイブコーディングはイノベーションを加速させるのと同じくらい簡単に侵害を加速させる可能性がある。
Crystal Morin氏は「ツールは使え、人間を信頼せよ」がモットーであると述べている。その言葉通り、STRIDEやOWASPのようなセキュリティフレームワークとチェックリストやセキュリティ対策にもAIを使用し、進化するニーズに対応するようレビュー慣行を適応させることで、AI駆動のコーディングがセキュリティの負債ではなく、創造性の加速装置であり続けることを約束してくれるだろう。
参考情報
The New Stack「Securing the Vibe: Reducing the Risk of AI-Generated Code」
https://thenewstack.io/securing-the-vibe-reducing-the-risk-of-ai-generated-code/
- 2025 GenAI Code Security Report ASSESSING THE SECURITY OF USING LLMS FOR CODING
https://www.veracode.com/wp-content/uploads/2025_GenAI_Code_Security_Report_Final.pdf ↩︎ - the state of Secrets Sprawl 2025 https://www.gitguardian.com/state-of-secrets-sprawl-report-2025 ↩︎
- Cybersecurity Risks of AI-Generated Code https://cset.georgetown.edu/publication/cybersecurity-risks-of-ai-generated-code/ ↩︎
- Vibe check: The vibe coder’s security checklist. Retrieved from https://www.aikido.dev/blog/vibe-check-the-vibe-coders-security-checklist ↩︎
- Passing the Security Vibe Check: The Dangers of Vibe-Coding with LLMs. Retrieved from https://www.databricks.com/blog/passing-security-vibe-check-dangers-vibe-coding ↩︎
- 20 security best practices for vibe coding. Retrieved from https://appwrite.io/blog/post/vibe-coding-security-best-practices ↩︎